【読書シリーズ📖】『妙好人』鈴木大拙③~無所得の所得底~
前回、栃平ふじさんの詩を紹介しながら、深川倫雄和上のご法話を合わせてお伝えしました。
今回は、p17~「1-2_三戸独笑と聾唖の香林保一との問答」を読んでいきます。三戸独笑さんと、香林保一さんの問答が紹介されます。
妙好人の特性の今一つは、学得底に重点をおかないで、その無所得の所得底をありのままに吐出するところにある。それでその所得底には禅者のに似たものが窺われる。「ありがたい、ありがたい」で、いつも受け身を味わっているのかと見れば、忽如としてそれを「うそのうその大うそ」として、一撃の下に撃砕し去ることがある(p17) ※適宜現代語に改めています。
キーワードは、「無所得の所得底」かと思います。言い換えてみれば、「全てを手放している、しかしなお全て満たされている」といったところでしょうか。
妙好人の言葉には、確かに、自らのコロコロ変わる心持ちを「嘘」と表現されることが多々あります。面白いですね。
普通、我々は、私の中に確かなものを築こうとします。人生経験を積み、トライアンドエラーを繰り返してきたその価値観によって、自分特有の「正解」を持ちます。その正解が、強ければ強いほど、固ければ固いほど、格好の良いものに見えます。一時期、テレビでも、論破が流行りましたね。

私の中にある確かなものこそ、人に誇れるものだと一見思いますが、「その頑(かたく)なな思いこそが、自らを縛り、人を傷つける最大の武器なのだよ」と教えてくれるのが仏教でもあります。
だからこそ、前回の栃平ふじさんも「鬼の子」という表現をされていました。
妙好人として有名な、島根の浅原才市さん(1850~1932)も、周りの人が「肖像画を描きたい」と見せてきた自分の肖像画の下書きに、「角(つの)が足らん」と、「鬼の角を書き加えてもらった」というエピソードもあります。(見てください。才市さんの頭に角が生えています。)

(温泉津めぐりHPより)
普通、肖像画は、「格好よく描いてほしい」と思うものですよね。少しでもしわを少なく、ライトを当てて、プロフィール画像も設定するものではないでしょうか。
他人からは「優しい人だ。尊い人だ。素晴らしい人だ。」と褒められても、仏様の前に座り、自らの本性を確認する時、「鬼の本性を持っている我が身でもある」ということを深く見つめておられました。
と、同時に、その私こそを目当てとして、決して見捨てないとはたらくお慈悲の仏様が、「南無阿弥陀仏の仏様」であったと喜ばれました。
才市さんの詩にこんなものもあります。
・なんともない うれしゆもない ありがともない ありがとないのを くやむじやない
(なんともない 嬉しゅうもない ありがたくもない ありがたくないことを 悔やむじゃない)
・ありがたいのわ みなうそで なんともないのが ほんのこと これほど安気なことわない なむあみだぶつなむあみだぶつ
(ありがたいのは みな嘘で なんともないのが 本当のこと これほど安気なことは無い なむあみだぶつなむあみだぶつ)
有難いという思いも条件ではない。こちらの人間の側の心持ちを条件にはしないのが、浄土真宗の御本尊、阿弥陀仏の特徴です。その仏様の思いに任せることこそ、「安気なこと」究極の豊かさを味わい境地と頂いた言葉でしょう。
話を戻します。
三戸独笑さんと香林保一さんとの問答です。香林保一さんは、耳が聞こえず、話も出来ませんので、筆談だったようです。まず、香林保一さんが、一切耳が聞こえないことと、話が出来ないことを伝えるところから問答が始まります。
三(三戸独笑)「そして耳も聞えませぬか。」
香(香林保一)「一向聞えませぬ。」
三「耳もよく聞え、また自由に問はるる口を持ちながら、真に聞く人の少ないのに、あなたはどうした宿縁の厚い御方でしょうか。」
香「耳に聞くから逃げてしまふ。御法は耳に聞くのでなくて心に聞くものです。」
三「恐れ入ります、誠に仰せの通りです。とかく耳に聞く者心に聞かず、自由が叶うて却って 御法を聞かず。貴下の如き不自由な人が却って仕合せであります。」
香「私は不具者で仕合せではありませぬが、尊い御慈悲を聞かせて貰ふのが何よりの大仕合せです。」
三「いかにもその通りです。然らば心に御慈悲が聞こえましたか。」
香「聞こえるまでもなく、聞かさにゃ置かぬの御慈悲を信じさせて貰うたのであります。」
三「同意同感です。時に貴下は、いつ頃から御法が気にかかり出しましたか。」
香「十六歳の時、盲啞学校より博多に参り、万行寺に泊りまして、七里和上様(七里恒順和上のこと)の懇ろなる御縁を頂き、遂に因果応報の談に遷り、和上様は涙を流して「お前様は前生は何をしておったか、 またどこから来られたか」と問はれて、さっぱり返事ができぬので、「教へて下さい」と申しましたら、「強盗殺人の大悪事をした報で、啞に生れて来たのである」と申されました。「何処から来たのですか?」と問うたら、「地獄」といわれ、「今度は何処に行きますか?」と重ねて問へば、また「元の地獄」と申さるるので、あさましいやら悲しいやらで、泣いてばかり居りました。それがそもそもの動機となり、逢ひ難い御法を一心に求める気になりました。その後、 御弟子の西行様にも二年ほど付いて回りました。」
三「委細な、しかも明らかな御答え、お懐しうあります。御同情申しますが、最後に何か味わわれましたか。」
香「三界六道を迷ひつつある事と、それを憐れみ下さる御親のある事とを知らせていただきました。」
三「いよいよ真実の御親と思はれますか。」
香「それは思はれる時と、思はれぬ時とありますが、思はれても思はれまいでも、真実の御親である。」
三「わたしは厄介仏の因果者と思ふ。」
香「厄介仏の御世話になる奴もやっぱり厄介者である。それで因果の掛かり合いで仕方がない。」
三「因果仏の極楽に参りたいですか。」
香「御浄土にさのみ用事はなけれども、救わせてくれよの御親なら、お互いに参ってあげようじゃないかえ、御同行。」
三「御浄土参りの同行ならまっぴら御免。地獄行きなら同心しよう。」
香「嫌でも自性なら、出た巣に帰るは当然じゃが、弥陀が邪魔して行かして呉れぬで困るのよ。」
三「その邪魔をする親爺はどこに居ますか。」
香「たった六字に細められて、逃げる此奴(こやつ)に付いておる。」
三「付いておるやうな繊弱い親爺が、生死の大問題を引き受けますか。」
香「言葉にかけると左様言いたいが、吾(われ)の御慈悲か御慈悲の吾か、いかん。」
三「誠に飛び立つ思ひがする。吾ゆえの御慈悲なれば、吾が先、また御慈悲より知らせていただいた吾なれば、御慈悲が先のように申したいけれど、吾も嘘、御慈悲も嘘、嘘といふ事も丸々赤うそ。」
香「嘘はどこまでも嘘なれど、嘘の吾あるゆえに助かるので、嘘のままが有難いではありませぬか。」
三「助かると吾と二つなし。」
香「書けば二つで心は一つ、信機即ち信法である。」
※適宜現代語に改めています。括弧は筆者。
七里和上が、自らの過去世の悪業を悲しみながら、また香林保一さんも「地獄生まれの人であったか」と共に涙する経験をきっかけに、香林保一さんは、浄土真宗の教えに触れていかれました。煩悩によって、自分を傷つけ他人を傷つける人間は、地獄行きの身ではあるが、その私を「離しておかぬ」と届く、南無阿弥陀仏の仏様に出遇うのが浄土真宗です。
自分の心持ちほど、あてにならないものはありません。状況によって環境によって、コロコロ変わるこの心持ちを、阿弥陀様は往生成仏の条件とはされませんでした。
「嫌でも自性なら、出た巣に帰るは当然じゃが、弥陀が邪魔して行かして呉れぬで困るのよ。」と、阿弥陀様のお救いを、「邪魔」と表現しながら喜ばれるその言い方は、他力のお救いの力強さを語っています。私の煩悩も邪魔にならないそのお救いだからこそ、「吾も嘘、御慈悲も嘘、嘘といふ事も丸々赤うそ。」と、自力の無功性を述べています。
古来、浄土真宗のお救いを、「法体独用 機受無作」と表現してきました。言い換えれば「阿弥陀様の力100% 衆生の力0%」です。
私の命の中に至り届く南無阿弥陀仏を、素直に頂き信知する状態こそ、「全てを手放している、しかしなお全て満たされている」また、鈴木大拙氏の言う、「無所得の所得底」ではないでしょうか。
また、忘れてはならない大切な言葉がありました。「耳に聞くから逃げてしまふ。御法は耳に聞くのでなくて心に聞くものです。」
御聴聞とは、耳で聞いて覚えることではありません。この心に響くおみのりを聞くんですね。
(少し聞きにくいですが、鈴木大拙氏の声をどうぞ。)
〈参照サイト〉
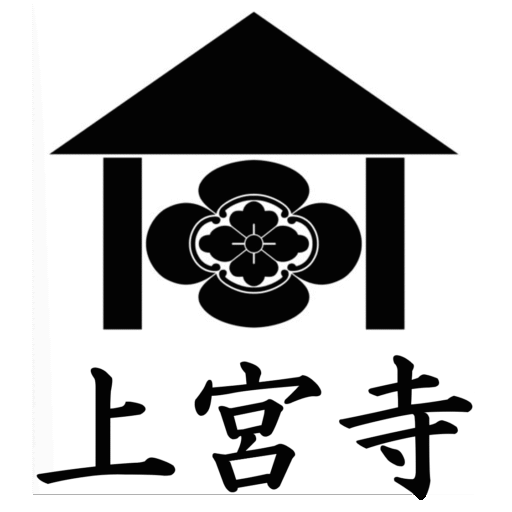
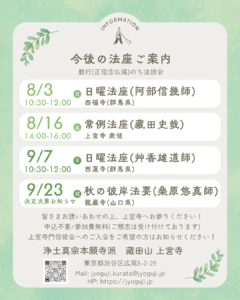

“【読書シリーズ📖】『妙好人』鈴木大拙③~無所得の所得底~” に対して1件のコメントがあります。