【読書シリーズ📖】『妙好人』鈴木大拙⑫~倫理と宗教~
前回は、「悪魔の行動原理」と題して、敗戦後の日本に流れる、危うい人間感覚と、それ以上に大切な、霊性的な感覚について窺いました。
今回は、p38~「2-1_妙好人と日本的霊性なるもの」「敗戦後の日本人に襲い来るもの」の続きを読んでいきます。
まず、物質的な面ばかりが大切にされる社会が語られます。物質とは、政治、経済、工業技術などです。その際に、宗教がそっちのけにされることに警鐘を鳴らします。
政治や経済や工業技術が重んぜられて、宗教はそっちのけにせられる。それから宗教の面でも、各種の救済事業のようなものが盛んに営まれて来る、「隣人愛」なるものが高唱せられて来る。内面的生活————— これが宗教生活の本質だと思われるが――、それが余りに多くの注意を払われないでいる。宗教の倫理面のみが宗教の全部であるかのようにやかましくいわれる。それもわるいとはいわぬが、宗教はただただそれだけのもののように考えられて来る。それが物足りぬ。(p39)
倫理的な側面のみを指して、「宗教」を捉えることに対して、厳しく意見されています。

「機械は、スイッチを押せば動く。壊れたら、捨てられる」の図
宗教とは、人間生活に「役に立つ」とか、「人の為」と、倫理的な面もあるだろうが、主眼は、内面的生活であると述べています。

「自己を見つめ続けた達磨大師の図」
人々への影響力の与え方については次のように述べられます。
今までの神道は死んだものとして、それにつぐ仏教もやがては同じ運命に遭遇することであろう。彼らの中には今日の若人達を刺激するものは何もない。東洋の伝統は置き去りにして、これからは、動くもの、働くもの、外に現われ出るもの、合理的なもの、合目的的なもの ―――これでなければいけないというふうに考えられて来た。 このような次第で、東洋的またはことに日本的ともいってよい霊性的自覚の世界は閑却せられた。 (中略)今の若人達の参考に供したいと思うだけでない。実は、働くこと、考えるこ と、外来の刺激に興ずること、自然の「征服」に没頭すること、理性の外に天地なしときめてかかること、このような性格の所有主である欧米の人々、またその一部のキリスト教徒などに対して、参考の資料を提供したいと思ってのことである。霊性的自覚の世界は、東西とか、古今とかいう制約を受けない世界である。(p40)
宗教の世界を、合理的な感覚で捉えることに、やはりここでも警鐘を鳴らしています。そのような感覚で、宗教が考えられてきたから、「霊性的自覚の世界は閑却せられた。」と、考察されています。
合理的な思考に役に立てるのが、宗教ではありませんよ。
世界を問わず、古今を問わず、生命がそこに存する限り、宗教的問題は存在します。
それは、若者であろうと、キリスト教徒であろうと、関係のない問いです。
この不思議な命が、生きて、死んでいく。
ここに、向き合うことが、宗教であります。内面的生活であります。
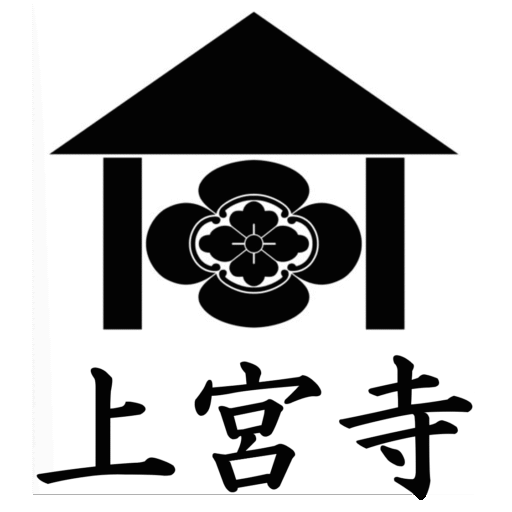
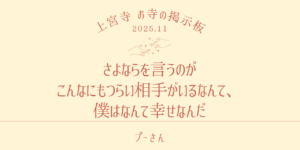

“【読書シリーズ📖】『妙好人』鈴木大拙⑫~倫理と宗教~” に対して1件のコメントがあります。