【読書シリーズ📖】『妙好人』鈴木大拙⑩~浅原才市~
前回は、「浄土真宗の今後」を考えてくださった鈴木大拙氏の言葉を確認し、妙好人の生き方、妙好人が大切にしたものを考えました。
今回は、p37~「1-9_浅原才市」を読んでいきます。
皆さん、浅原才市(あさはら さいち)さん(1850~1932)はご存じでしょうか。前にも登場したことがあります。
自分の肖像画に、鬼の角を加えたという、一見、常軌を逸したかに見えるエピソードを持つ妙好人です。自分の顔に、鬼の角を加えてほしいと希望する人がいるでしょうか。それほどまでに、自分の心の奥に潜む煩悩の鬼に、向き合われた方でありました。
浄土真宗の念仏者は、救いの光を仰ぎながら、そこに映される自分の影の大きさを見つめていく教えです。

島根県の温泉津(ゆのつ)の方で、安楽寺住職であった梅田謙敬和上の導きで、お念仏の人生を歩まれました。
最も有名な詩が、これだと思います。
かぜをひけば せきがでる
さいちが ごほうぎのかぜをひいた
ねんぶつのせきがでるでる
この詩について、他のブログで考えたことがありますのでぜひご覧ください。
「南無阿弥陀仏」「なんまんだぶつ」とお念仏する姿こそが、ご法義が私に至り届く姿でありました。そのことを素直に聞き受ける人を、妙好人と申します。
浅原才市なる人の覚帳を紹介することにしたい。(中略)この書に採録した翁の詠草というべきか、詩篇または歌章というべきか――自分にはちょっと好い名目が見つからぬ、 吐出底(Utterances)とするとよいがとも思う。(p37)
才市さんの詩について、鈴木大拙氏は、吐出底という名目で述べられています。聞いたことのない単語でした。おそらくその方の思いを、「素直に隠さず吐露した文章」ということでしょうが、確かにそうですね。
才市さんは、誰かに見せようと思って詩を書いていません。その思いは、仕事の最中にゴミくずになっていく、カンナくずに書きつけられていたのですから。見せたい、伝えたいという思いは、少しはあったかもしれませんが、一番は、自らに届いた阿弥陀様を、自らがまた確認していく。そこにあったでしょう。
その書きつけた文章は、「口あい」とよばれました。
仏と話をするときは 称名念仏 これが話よ
日々の生活の中で、阿弥陀様と出遇いながら、苦楽を超えて生き抜いた人生でありました。
その中でも私が大好きな口あいを紹介します。これも、仏様と会話しながら書いた文章だと思います。凄い文章です。もうその人生は、決して独りではありません。どこまで行っても、仏様と二人連れ。どれほど私が自分の人生を見失おうとも、私を見失わないお慈悲を味わう人生の豊かさを歌えてくれてもいます。
「さいちよ うれしいか ありがたいか」
「ありがたいときゃ ありがたい なっともないときゃ なっともない なっともないときゃ どがあすりゃ どがあもしようがないよ なむあみだぶつと どんぐりへんぐり しているよ」(梯實圓『妙好人のことば』参照)
この歌を初めて聞いた時の感動が蘇ってくる思いがします。
そうか、浄土真宗のお救いとは、「こちらの心持ちを確かにしていくことではないのだな」と、まざまざと教えられました。
「嬉しい」とか「ありがたい」など、これは我々の心持ちです。
「何ともないときは何ともない」それをどうしようもない。どうしようもないながら、お念仏しながら、右往左往しているよ。
しかしただ、迷っているのではありません。どんぐりへんぐりしているのはどこかと言うと、「阿弥陀様の懐の中」でありました。その喜びが形になったのが、「なんともない」という言葉であったかと思う時、浄土真宗のお救いの凄み、他力のみ教えの奥深さに、感動します。
〈参考サイト〉
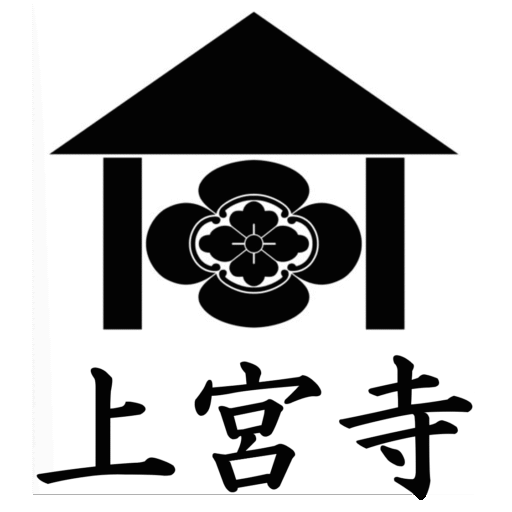
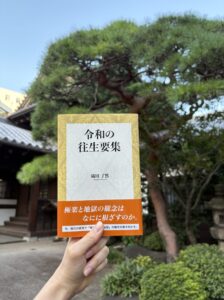
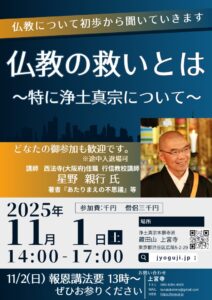
“【読書シリーズ📖】『妙好人』鈴木大拙⑩~浅原才市~” に対して1件のコメントがあります。