【読書シリーズ📖】『妙好人』鈴木大拙⑭~霊性的自覚・浅原才市~
前回は、「霊性的自覚の世界」と題して、鈴木大拙氏が使われる「霊性的世界」という言葉について考えました。
今回は、p41~「2-2_霊性的自覚の世界‐浅原才市‐人間の罪悪感と倫理‐他力宗と罪悪感」の続きを読んでいきます。
今回は、以前にも登場した、浅原才市氏が、再び登場します。
才市の霊性的自覚の世界に入ることは容易でないが、日本人の中にこのようなものがあることをわれらは知っておいてよいのである。(中略)人間の天地は必ずしも科学や合理性や合目的性でつくせぬもののあることを示唆せんとするのである。(p42)
才市の感覚、その世界を、「知っておいてよい」と、鈴木大拙氏が勧める内容とは何か。そこに迫っていきたいと思います。
彼(才市)の環境には真宗的なものが漂っていた。警察との関係で、「罪業」の意識は彼の心に深まり行った。しかし、真宗及び一般に罪業というのは、必ずしも社会的・倫理的意義でいわれるのでない。もっと深いところから出るので、荀くも人間である以上は、残るところなく罪業の存在なのである。神の存在でさえも罪業性を帯びぬとはいわれないのである。(中略)人間倫理の矛盾性も、神がキリストにならなければ人間を救われなかったのも、弥陀の誓願の永劫に渉って尽くることのないのも皆、人間存在、或いは宇宙存在そのものの根源に潜在する罪業から出発するのである。宗教はたんなる倫理や社会的罪悪感から出るものでない。必ずしも出ないとはいわぬが、それでつきているとはいわれない。倫理から宗教は出ない、従って倫理で宗教をつくすわけに行かない。 才市が三十年に渉る精神的苦闘の根本は実に人間そのものの存在にあるのである。たんなる倫理性のものでないことをことに強調したいと思う。(p43)
※適宜現代語に改めています。括弧は筆者。
やはりここでも、倫理と宗教の関係について言及されます。
人として生きる以上、皆、罪業の存在であるが、その罪業の延長で宗教の道が存在するのではないと言います。倫理を尽くした結果ではなく、宗教的苦闘がそこにはあったのだそうです。
宗教意識が深まるというは、人生に対する不安の念が強まるという義である。真宗では、「罪業深重、地獄必定」という形式で聴聞の人々に迫って来る。そうしてこの地獄なるものが必ずしも具体的にどのような形で描かれるということはないにしても、何か死後に恐ろしいものに出会うといわれる。これに反して浄土または極楽であるが、これもまたお経に記されているような一面頗る物質的なものとは限らぬが、何か楽しい境界と感ぜられる。この二つの、相対照し、矛盾したものが、死後に現出するといわれるが、その実、現在のわれらの生活そのものがこの矛盾を孕んでいる。 現在が未来にうつるのか、未来が現在をてらすのか、いずれにしても、人間は両者の間に頭出頭役していることだけは疑われぬ。しかし並大抵の人々はこれを意識の上に明白にしてはいない。これ には優秀な知性と潤沢な情性が必要である。普通には何だか不安だということですんでいる。才市の場合、地獄や浄土がどのような形でその心に描かれたかは、もとよりわからぬが、「罪業深重」はあった。(p44)
鈴木大拙氏の言う、「宗教意識」とは、人生の不安に向き合うことであると言われます。
現実に生きる我々は、矛盾を抱えながら生きています。「今生きている」という当たり前のことも、考えてみれば、不思議です。呼吸をすることが当たりまえになり、生きている感動も普段は少ないですが、おそらく、正しく命を見つめるならば、生きていることも、死ぬことも、当たり前のことではなく、人知を超えた不可思議なことなのでしょう。
血液の細胞は、4か月で入れ替わるそうです。睡眠中は、基本的に意識がないそうです。
そんな不思議な体と心を抱えながら、我々は、生きているのですね。
次は、才市の、宗教的、悪戦苦闘を窺っていきましょう。
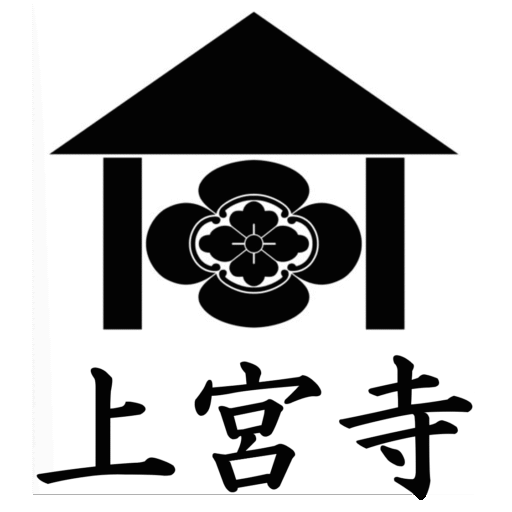
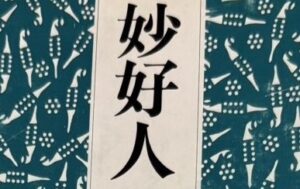
“【読書シリーズ📖】『妙好人』鈴木大拙⑭~霊性的自覚・浅原才市~” に対して1件のコメントがあります。