【読書シリーズ📖】『妙好人』鈴木大拙⑥~『教行信証』と『歎異抄』の二潮流~
前回は、キリスト教と浄土真宗とを比較しながら、その共通点と、異なる点を、鈴木大拙氏の言葉に依りながら確認しました。
今回は、p26~「1-5_真宗における二潮流、教行信証系と歎異抄系〜有智と無智」を読んでいきます。
真宗には、開教の始めからすでに二つの主流があったものと考えられる。これは著者のまだ十分に検討しない課題であるが、どうもそのように感じられるのである。主流の一つは、『教行信証』系である。今一つは、「和讃」や『歎異抄』及び「消息集」に通ずる系統である。(p26)
浄土真宗の流れに、二つの潮流あることを指摘します。
一つが、『教行信証』
一つは、「和讃」や『歎異抄』及び「消息集」
どれも、浄土真宗の聖典の中に収められるものであり、大切にされてきた書物であります。
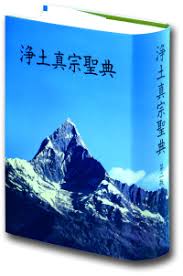
(『浄土真宗聖典』いわゆる『註釈版』です。浄土真宗の僧侶となるにあたって全員に配布されます。)
漢文で書かれる『教行信証』が、学問的な書物であるのに対して、学者ではない一般の門徒に向けて書かれたのが、それ以外の書物であると分けられます。
漢文―自分らの言葉でない、外からの借用物で、他所行(よそゆき)の衣装である―を著ないで、平常服(ふだんぎ)のままで日用の挨拶に使う言葉で、中(うち)からのままを、極めて率直に語り得るところのものである。彼はそれを自分の周囲に親しく参集し来る人達と語りたかったのである。 知性の甲殻をかぶらない、論理の葛藤に捉えられない主体的経験を、ありのままに、赤裸裸に吐出する機会を、彼は望んでいたのである。それは、『教行信証』に現われないで、最も的確に『歎異抄』 に現われているのである。「和讃」では、なお飾りものがついている、文学的工作が用いられている。『歎異抄』には純粋に親鸞の日常性が現われている。この点でこの一書(歎異抄)が他力宗の教典として最も重要である。(p26)
『教行信証』が、よそ行きの衣装としたとき、『歎異抄』は普段着であり、その日常の言葉遣いにこそ、親鸞の日常性が現れると述べられます。本人の文章ではないにせよ、本人から漏れ出た日常の言葉を、唯円が書き留めたことが評価されています。
妙好人の流は『歎異抄』から出るが、『教行信証』からは湧いて来ない。他力宗の真面目は、宗学の老匠達がしゃちょこばって坐わりこむところよりも、むしろ百姓教信が夕顔棚の下で片肌ぬいで涼風に浴するところに汲み取るべきであろう。もとより学匠達もなくてはならね、これがなければ宗教的体験は知性の上に確立するわけに行かぬ。そうしてその確立は人間の叡智が要求してやまないところである。(中略)しかし、これは日本人に限られた趣味かどうかはわからぬが、侘しい茶室で、素朴な茶碗で、一服の茶を喫するところに、われらは一種のゆとりを楽しむことができる。妙好人の他力的安心にはこれに似たものを感ずるのである。(p28)
この文章からも、鈴木大拙氏が、学問と信仰とを切り分けて考えていたことが窺えます。学問を究めることも大事だが、浄土真宗の救いとは、学問の延長にあるものではなく、日常に染み込んだ、肩ひじ張る必要のない信心であるということです。
私自身、恩師に言われた言葉として、今も覚えている言葉があります。
「学問の延長に信仰はあるのではなく、信仰の延長にいくらでも開かれてくるのが真宗学です。」
という言葉です。「知識の獲得で救われるのではありませんよ」と、教えてくださった言葉だと受け止めています。
阿弥陀様のことや、浄土真宗の体系を、知り抜いて救われるのではなく、逆に、知られぬいて、救われるのだと、味わっています。
(浄土真宗の)対機となるものは何といっても、「物知り」よりは「物知らず」である。始めから何か「物知り」などという自覚のあるところでは、能力は容易に受けられぬ。 が、もとより「自分は無知である」と覚悟している胸の中へは、割合に浸透し行き易いものがある。 (p29)
妙好人とは、「物知り」より、「物知らず」であると言われます。そして「物を知っている」人には浸透しないお慈悲が、「物知らず」には素直に浸透していくのだと。
確かにその面はあると思います。「私は物を知っている人だ」と自負がある人に新しい知識は入りません。新しい知識があることを認めることは、それまで頑張った自分を否定することにもなるからです。しかし、「私は知りません」と自負する人は、新しい知識を「ありがとう」と受け入れていくことが出来ます。
単に、日常の知識を言っているのではありません。阿弥陀様のお慈悲を聞き受けようとした時、「自分の知識こそ全てだ」と思う人には、到底受け入れられないと思います。なぜなら、人間の常識からはかけ離れた、荒唐無稽に思えるストーリーが描かれる経典を大事にするからです。
しかしその「自分は間違いない」と思っている知識は、どこまで一貫しているものなのか。命の問題に関しては、実は何も理解していないのではないか、とも思うのです。
「物知らず」という言葉に関してです。「門徒ものしらず」(内容は、「門徒もの忌み知らず」俗信や迷信に振り回されない真宗門徒を指す用語)という言葉もあります。
私としては、「ただ物を知らない、知識のない人」というよりは、「物知られ」だろうと感じます。こちらが分かっていくのではない。こちらを見抜いたお慈悲あることを喜び、知る側ではなく知られる側に安住しながら、お念仏申すのです。お慈悲の眼に見抜かれた我が身を頂く人を妙好人と言うのです。
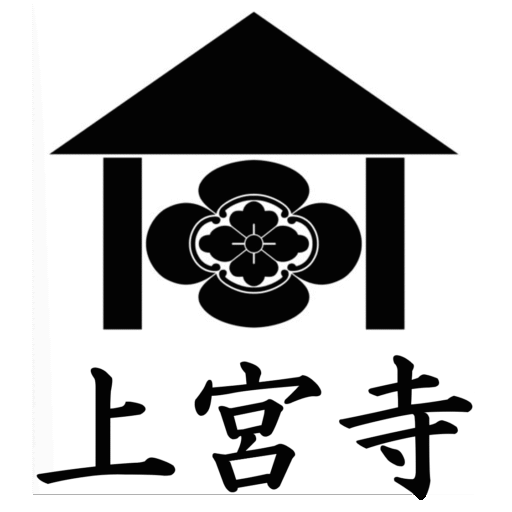

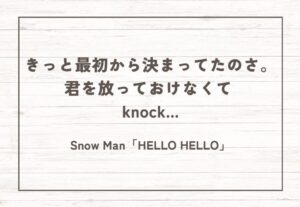
“【読書シリーズ📖】『妙好人』鈴木大拙⑥~『教行信証』と『歎異抄』の二潮流~” に対して1件のコメントがあります。