【読書シリーズ📚】『妙好人』鈴木大拙⑧~じごくごくらく ようじなし~
前回は、宗教という大きなものを分類した時の特徴、また浄土真宗の妙好人の特徴を、鈴木大拙氏の言葉に依りながら、確認しました。
今回は、p31~「1-7_現在日本における妙好人ー小松の森ひな」を読んでいきます。
妙好人は割合にひろく日本に分布しているようである。子細に調べて見ると、現在の日本人中にもかなりに多数あると推定せられる。そうして、彼らの中には所信を文字に表わすのが少なからぬのである。僅かに平仮名を知っているだけで、それを自在に使うのである。(p31)
※漢字は適宜現代語に改めています。括弧は筆者。
第1回の投稿でも触れた、妙好人の多さに、またここでも鈴木大拙氏が触れています。
例を挙げると、加賀の小松に森ひなさんという六十一歳の婦人がある。子と別れるに当り、口授して彼に書き取らしめた信念の歌がある。(p31)
ここで例として、石川県の森ひなさんという妙好人の歌を挙げます。文字を代わりに子供に書いてもらいながら、その思いを吐露しています。
- おさないときより まいりはすれど なんのきもなく きいていた われのこころの なやみのために おてらまいりに ふみだした
- われのちからで でるとはおもうた そうじゃなかった おやちから たりきたりきと おもうていたが おもうたこころが みなじりき じごくきらひの ごくらくのぞみ のぞむこころも みなじりき
- こうかああかと はかりていたが はかるが(の)でない ただのただ ああありがたい なむあみだぶつ
- われがめくらのこしぬけゆえに おやのちからで よがあけた ああありがたい なむあみだぶつ
- となへるしようみよう われがとおもうた そうでなかった みだのよびごえ ああありがたい なむあみだぶつ
- じごくいちじよと おもうてみれば じごくごくらく ようじなし
- あみだによらいと つきひをおくる いつのなんどき ひがくれようと ああ ありがたい なむあみだぶつ ごおんとうとい なむあみだぶつ
- われのちからで かいたのでない おやのちからで かきあげた
いかがでしょうか。
ぜひ声に出して読みたいリズム感、息遣いです。
解説すら邪魔になるような、見事なお味わい、ご讃嘆ではないでしょうか。
「称へる称名われがと思うた、そうでなかった、みだのよびごえ、ああ、ありがたい、なむあみだぶつ」。
これはどのような他力宗の信者からでも、皆聞くところ、またその口にするところであろうが、それがいわゆる目に一丁字ないと考えられる人の口から、自然に発露するところを見ると、 如何にもと有難い気分になる。それから引きつづいて、「地獄一定と思うて見れば、地獄、極楽、 用事なし」と言い放つ。如何にも大胆な信仰表白と思われよう。(p35)
「南無阿弥陀仏(なんまんだぶつ)」とお念仏するのは、自分の力だと勘違いしていた。そうではなかった。阿弥陀様の「あなた一人忘れはしないよ」という慈悲の思いが私に届いている姿が、お念仏するという行為なのだと、親鸞聖人は生涯をかけて伝えて下さいました。その喜びの吐露に、鈴木大拙氏も、「いかにもと有難い気分に」なったんだそうです。
また、「地獄極楽、用事なし」の言葉にも触れています。
じごくいちじよと おもうてみれば じごくごくらく ようじなし
自らの行いや、胸の内の心持ちを振り返れば、仏様に顔向けできないようなことも持っている。その煩悩の思いは時に人を傷つけている。自らをも見失う時もある。
しかし、「仏様に見抜かれ、抱かれているのだから、連れて行かれる場所が、地獄であろうが極楽であろうが、そんなに大きな問題ではない」ということでしょう。
まるで、『歎異抄』の一節を聞いているかのようです。
念仏は 、まことに浄土に生まるるたねにてやはんべ らん、また地獄におつべき業にてやはんべるらん、総じてもて存知せざるなり。(『歎異抄』第2条)
自分のはからいによって救われていくのではない。仏のお慈悲を頂くところに救いを味わう、他力のみ教えでありました。
親鸞の表明は一種の宗教的矛盾として見るべきもの、またその故に容易に知性的解釈を許さぬものがある。それが明らかに何の造作もなく市井の一老婦人の口から送り出ずること、他力信心が如何に不思議な浸透性に富むかを見るべきではなかろうか。
またここで、妙好人、浅原才市さんの詩も紹介しています。
「さいちよい。へ。たりきをきかせんかい。」
「へ。たりき、じりきはありません。 ただいただくばかり。」
これなども、『キリストを倣う』の著者、トマス・ア・ケンビスが「わが希うところは、悔い改めの定義でなくして、これを心に感ずることである」というのに比すべきではなかろうか。
「自力」、「他力」とこだわる所には、自らの計らいしか、無いのでしょう。その思いの延長に、救いがあるのではないよ。「仏様の思いを、ただ頂くことこそ、浄土真宗のお救いですよ」と、スパッと言い切られたような言葉です。
先に見た、ひなさんの言葉ともかぶります。
われのちからで でるとはおもうた そうじゃなかった おやちから たりきたりきと おもうていたが おもうたこころが みなじりき じごくきらひの ごくらくのぞみ のぞむこころも みなじりき
私は、この詩が、ひなさんの詩の中でも、特に好きです。
特に好きなのが、「たりきたりきと おもうていたが おもうたこころが みなじりき」です。
「他力なんだ。他力なんだ。」と、力むところに、他力信心はありません。
お念仏の一声も、阿弥陀様のお慈悲と、さまざまなお育てが無ければ、私の所には絶対に届かなかった。こちらが忘れようとも、こちらを忘れない思いがあったから、今お念仏できているのだという、命の根本で地に足がつくのが、他力信心であると、私は味わっています。ここに、「地獄、極楽、自力、他力」人間の言葉や、はからいを超えた、救いの味わいがあります。
このことを、鈴木大拙氏は、「らくの境地」と表現し、妙好人を讃嘆されました。
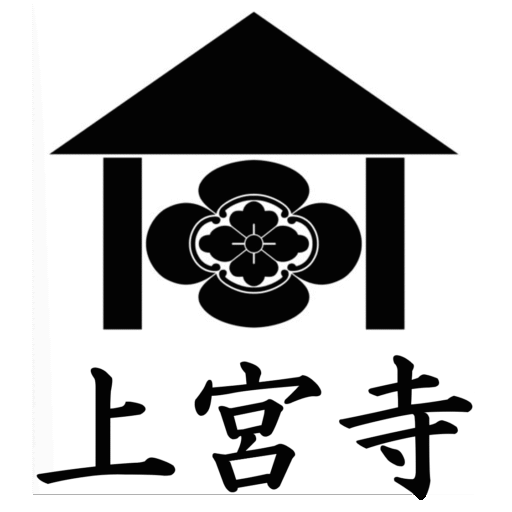
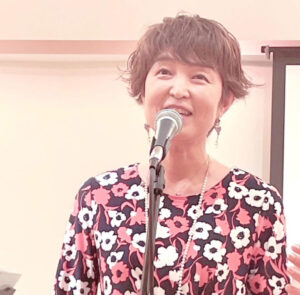

“【読書シリーズ📚】『妙好人』鈴木大拙⑧~じごくごくらく ようじなし~” に対して1件のコメントがあります。