【読書シリーズ📚】『妙好人』鈴木大拙⑨~見えぬけれどもあるんだよ~
前回は、石川小松の森ひなさんの味わいに心を寄せながら、他力のお念仏とは何かを考えました。
今回は、p36~「1-8_他力宗の今後」を読んでいきます。
鈴木大拙氏は、浄土真宗を、「他力宗」と呼びます。第1章もクライマックスに近づきました。引き続き、読んでいきます。
ことに日本が今日置かれている立場―――最早閉じ込められた「日本」ではなくて、世界的にその柵を取りはずした世界国民としての立場――から見て、他力宗(浄土真宗)の今後の活動は如何あるべきか。
※適宜現代語に改めています。括弧は筆者。
と、浄土真宗の、今後にまで心を配ってくださっています。鈴木大拙氏は、僧侶ではありませんでしたが、大乗仏教徒として、禅や念仏を大切にされました。その目線から見た時、これからの浄土真宗がどのようにあるべきかは、この本が書かれた時代が昔であるとはいえ、大切な課題であると感じます。
今までの他力宗そのままでも、その妙好人を産出する霊性的創造力の偉大さから見て、これを世界的に進出させなければならぬものがあるのである。ことに近代文化なるものが、人間性の外殻を破るに無能なこと、ただその相対性の面だけに接触するにすぎないこと、いうところの物質的生産面に停滞して、その下に流れているものを汲み取り得ないこと、ただ今までの歴史観の上に立つことを知るだけで、これから作らるべき文化に関して何等計画的なものを持たぬこと等に対して、他力宗の立場から、世界文化の上に寄与すべきものが少なからぬと信ずる。
鈴木大拙氏は、浄土真宗を誉めるに際して、「妙好人を産出する霊性的創造力の偉大さ」と述べられます。妙好人のような、宗教的な感性を育て上げるのが浄土真宗の強みであり、世界文化に寄与すべきとまで言われます。

鈴木大拙氏にここまで褒められる妙好人とは何か。改めて確認すると、それは「お念仏よろこぶ人」のことであります。特別な修行を積んだ修行者ではなく、日常の日暮らしを送りながら、お念仏を喜んだ妙好人たちの至った、精神的な境地とは、鈴木大拙氏をして驚かせるほどのものでありました。そのことについては、これまで何回も確認してきました。
物質的な側面を大事にする社会から漏れていく、「その下を流れているもの」に、アクセスすることこそ、全世界にとっての大切な課題だと、仰っているように思います。
「かんじんなことは 目に見えないんだよ」 (サン=テグジュペリ)
「昼のお星は眼にみえぬ。見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。」(金子みすゞ「星とたんぽぽ」)
目に見えているもの以上に、見えないもの達に包まれているのでしょうね。
妙好人が大切にした、わが身にはたらく仏様のお慈悲を、大切にして生きる妙好人の人生を、鈴木大拙氏はここで誉めておられます。
〈参照サイト〉
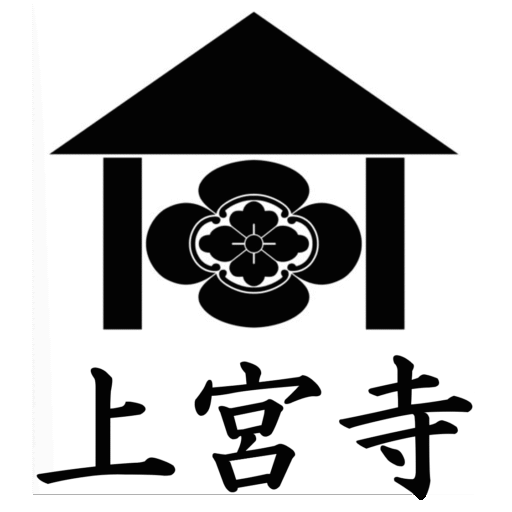

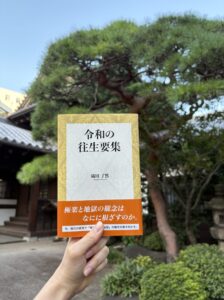
“【読書シリーズ📚】『妙好人』鈴木大拙⑨~見えぬけれどもあるんだよ~” に対して1件のコメントがあります。